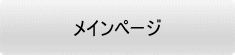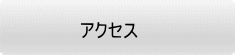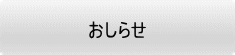予防接種
予防接種がご必要になられましたらまずはお電話を
予防接種
当院では【任意接種】【定期接種】ともに行っています。
【成人肺炎球菌予防接種(ニューモバックス)】
最近テレビCMでご存知の方も多いかと思いますが、日本人の死因の第3位は肺炎です。65歳以上の方は肺炎予防接種をおすすめいたします。 1回の接種で5年間有効で、自治体の補助も行われています。
・文京区民、75歳以上となる方で任意接種ご希望の際には4000円
・文京区で定期接種対象の方:平成27年度に65・70・75・80・85・90・95・100歳となる方は予診表が個別に送付されていますのでお持ちください。費用は4000円となります。それぞれ生涯1回のみ助成されます。1度接種している方でも、5年過ぎていれば再接種の必要があります。
*助成に関し、詳しくは文京シビックセンター8階
予防対策課感染症係 電話番号:03-5803-1834 までお問い合わせください。
【小児肺炎球菌予防接種(プレベナー)】
肺炎球菌は、集団生活が始まるとほとんどの子どもが持っているといわれるもので、主に気道の分泌物により感染を起こします。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、肺炎や中耳炎、髄膜炎などの重い合併症を起こすことがあります。 特に、髄膜炎をきたした場合には2%の子どもが亡くなり、10%に難聴、精神の発達遅滞、四肢の麻痺、てんかんなどの後遺症を残すと言われています。
また、小さい子供ほど発症しやすく、特に0歳児でのリスクが高いとされています。
現在、小児の肺炎球菌感染症に対するワクチンとして「プレベナー(」が使用されています。 肺炎球菌には、90以上の種類があり、それぞれ特徴が異なります。「プレベナー」には、特に重篤な肺炎球菌感染症を引き起こすことの多い、13種類の肺炎球菌の成分が含まれており、主にこれらに対して予防効果を発揮します。
【インフルエンザ予防接種】
日本では、インフルエンザは例年12月〜3月頃に流行し、例年1月〜2月に流行のピークを迎えます。ワクチン接種による効果が出現するまでに2週間程度を要することから、毎年12月中旬までにワクチン接種を終えることが望ましいと考えられます。当院での季節性インフルエンザの予防接種期間は接種期間は10月〜3月上旬です。 季節性インフルエンザワクチンでは、これまでの研究から、ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種した(13歳未満の場合は2回接種した)2週後から5カ月程度までと考えられています。成人は1回、13歳未満のお子様は2回接種となります。
【おたふくかぜ(ムンプス)ワクチン】
「おたふくかぜ」は、ムンプスウィルスに感染すると起こる病気です。「流行性耳下腺炎」または「ムンプス」とも呼ばれます。潜伏期は約2〜3週間前後ですが、発症6日前ぐらいからウィルス排出があるので、気づかぬうちに周囲に感染を広げている事があります。おもな症状は1週間程度続く耳下腺の腫脹とそれに伴う高熱です。ムンプスウィルスは全身のいろいろな所、特に神経組織や内分泌系腺組織に広がり、様々な合併症(髄膜炎・脳炎,難聴,膵炎,精巣炎・卵巣炎 等)を起こすことがあります。国立感染症研究所のデータをもとにおたふくかぜ患者の年齢別分布をみると、0歳児は少なく、年齢と共に増え、4〜5歳が最も多くなり、その後は減少します。3〜6 歳合計で全患者数の約60%を占めますので、推奨される接種時期としては、1歳で1回目を済まし、4〜5歳程度で2回目、の計2回接種がよいと考えられます。わが国では定期ではなく任意接種となっております。おたふくかぜ(ムンプス)ワクチンは生ワクチンですので、生ワクチン同士の接種には4週間以上あけてください。
【水ぼうそう(水痘)ワクチン】
平成26年10月より、こどもの定期接種に入りました。36か月までに2回接種します。水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、水痘帯状疱疹ウイルスというウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。空気感染、飛沫感染、接触感染により広がり、その潜伏期間は感染から2週間程度と言われています。発疹の発現する前から発熱が認められ、典型的な症例では、発疹は紅斑(皮膚の表面が赤くなること)から始まり、水疱、膿疱(粘度のある液体が含まれる水疱)を経て痂皮化(かさぶたになること)して治癒します。一部は重症化し、近年の統計によれば、我が国では水痘は年間100万人程度が発症し、4,000人程度が入院、20人程度が死亡していると推定されています。
水痘は主に小児の病気で、9歳以下での発症が90%以上を占めると言われています。小児における重症化は、熱性痙攣、肺炎、気管支炎等の合併症によるものです。成人での水痘も稀に見られますが、成人に水痘が発症した場合、水痘そのものが重症化するリスクが高いと言われています。
帯状疱疹の原因ウイルスもまた、水ぼうそうウイルスです。神経節にひそんでいた同ウイルスが、年齢を重ね免疫力が下がった年代に、神経に沿って休眠から覚め、悪さを始めます。帯状疱疹後神経痛という、強い痛みがのこってしまうことがあります。現在、帯状疱疹を予防するために同ワクチンを接種することは保険診療、定期接種ではみとめられておりませんが、海外の研究において、水痘にかかった事のある高齢者に水痘ワクチンを接種すると、その後は帯状疱疹が出にくくなるか、また神経痛の程度はどうか検証されています。ワクチン接種をおこなうと発症率は約半分に、発症者のうち神経後遺症が残る症例が約1/3になったことから、予防としての効果は十分に期待できそうです。
水ぼうそう(水痘)ワクチンは生ワクチンです。生ワクチン同士の接種には4週間以上あけてください。
【A型肝炎予防接種】
A型肝炎は、A型肝炎ウイルス(HAV)によって引き起こされ、これに汚染された水産物、汚染された水や氷、汚染された水で洗われた野菜や果物の経口摂食により感染します。海外の流行地では感染の可能性があるので、海外渡航される方、とくにアジア地域や水質の安全性が確保されていない地域へ頻繁に行かれる方や、そこで長期滞在をご予定の方に接種をおすすめします。A型肝炎ウイルスの潜伏期間は平均28日(15-50日)です。感染すると全身倦怠感が強くなり、黄疸、発熱、食欲不振、強い腹痛や下痢を発症し、重症となると1ヶ月以上入院が必要になる場合もあります。 接種回数は一般的に3回、2週間隔で2回、さらに6?24カ月後に3回目の追加接種が必要です。 3回接種にて抗体の持続期間は5年と言われています。3回目の間隔があくので、出発までに時間のない方は3回目接種を一時帰国などを利用して打たれることをおすすめします。
【B型肝炎予防接種】
B型肝炎ウイルス(HVB)は感染した患者の血液や体液と接触したり、感染した輸血を受けた場合、無防備な性行為を含む体液交換、消毒不十分な注射針や医療器具(医療行為、歯科治療、針治療、刺青、麻薬常習者などを含む)で感染する可能性があります。潜伏期間は平均90日で、多くの場合無症状か軽度の症状で終わりますが、全身症状として倦怠感、食欲不振、黄疸、吐き気、腹痛、関節痛がみられます。死亡率は1%で6−10%の確率で慢性化して、肝硬変や肝臓ガンに移行する可能性があります。接種回数は3回です。4週間の間隔で2回接種し、6ヵ月後に3回目の追加接種を行います。3回接種でHBs抗体が獲得できない場合は、5〜6ヶ月後に4回目の追加接種を行います。 医療関係で血液を扱う実習や医療関連のお仕事に就かれる際には必要となります。海外出張や留学の出発の前に時間がない方は、少なくとも2回目までは接種を済ませるようにしてください。ワクチンの効果を判定する抗体価の測定も行うことができますのでご相談ください。
【麻疹(はしか)ワクチン】
(麻疹風疹混合ワクチン;MRワクチン)
麻疹は、麻疹ウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。麻しんウイルスの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染で、その感染力は非常に強いと言われています。免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。感染すると約10日後に発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が現れます。2〜3日熱が続いた後、39℃以上の高熱と発疹が出現します。肺炎、中耳炎を合併しやすく、患者1000人に1人の割合で脳炎が発症、死亡する割合も、先進国であっても1000人に1人と言われていす。
麻疹含有ワクチン(主に接種されているのは、麻疹風疹混合ワクチン;MRワクチン)を接種することによって、95%以上の人が麻しんウイルスに対する免疫を獲得することができると言われています。また、2回の接種を受けることで1回の接種では免疫が付かなかった5%未満の人に免疫をつけることができます。さらに、接種後年数の経過と共に、免疫が低下してきた人に対しては、2回目のワクチンを受けることで免疫を増強させる効果があります。2006年度から1歳児と小学校入学前1年間の幼児の2回接種制度が始まり、2008年度から2012年度の5年間に限り、中学1年生と高校3年生相当年齢の人に2回目のワクチンが定期接種に導入されています。
今まで麻疹に罹ったことが確実である場合は、免疫を持っていると考えられることから、予防接種を受ける必要はありません。しかし、それが明らかでない場合にはご相談ください。抗体検査にて明らかにすることができます。定期接種の時期にない方で、「麻疹にかかったことがなく、ワクチンを1回も受けたことのない方」もご相談ください。平成2年4月2日以降に生まれた方は、定期接種として2回の麻しん含有ワクチンを受けることになりますが、それ以前に生まれた方は、1回のワクチン接種のみの場合が多いと考えられます。医療従事者や学校関係者・保育福祉関係者など、麻疹に罹るリスクが高い方や麻疹に罹ることで周りへの影響が大きい場合、流行国に渡航するような場合は、2回目の予防接種についてご相談ください。尚、麻疹を罹ったことがある人がワクチン接種をしても副反応は増強しません。もし、麻疹又は風疹の片方に罹ったことがあっても、他方には罹っていない場合、定期接種対象者は麻疹風疹混合ワクチン(MRワクチン)の接種を受けることができます。
MRワクチンは、生ワクチンですので、妊娠している女性は接種を受けることができません。また、妊娠されていない場合であっても、接種後2カ月程度の避妊が必要です。また、麻しんの単独ワクチン、風しんの単独ワクチンの接種に当たっても、妊娠している方は接種を受けることはできません。接種後2カ月程度、妊娠を避けるなど同様の注意が必要です。
【風疹ワクチン】
(麻疹風疹混合ワクチン;MRワクチン)
風疹は、風疹ウイルスによっておこる急性の発疹性感染症で、流行は春先から初夏にかけて多くみられます。潜伏期間は2−3週間(平均16−18日)で、主な症状として発疹、発熱、リンパ節の腫れが認められます。ウイルスに感染しても明らかな症状がでることがないまま免疫ができてしまう(不顕性感染)人が15−30%程度います。一度かかると、大部分の人は生涯風疹にかかることはありません。集団生活にはいる1−9歳ころ(1−4歳児と小学校の低学年)に多く発生をみていましたが、近年は多くが成人男性となっています。発疹のでる2−3日まえから発疹がでたあとの5日くらいまでの患者さんは感染力があると考えられていますが、感染力は、麻疹(はしか)や水痘(水ぼうそう)ほどは強くありません。風疹の症状は子供では比較的軽いのですが、まれに脳炎、血小板減少性紫斑病などの合併症が、2,000人から5,000人に一人くらいの割合で発生することがあります。大人がかかると、発熱や発疹の期間が子供に比べて長く、関節痛がひどいことが多いとされています。一週間以上仕事を休まなければならない場合もあります。
妊婦とくに、妊娠初期の女性が風疹にかかると、胎児が風疹ウイルスに感染し、難聴、心疾患、白内障、そして精神や身体の発達の遅れ等の障がいをもった赤ちゃんがうまれる可能性があります。これらの障がいを先天性風疹症候群といいます。先天性風疹症候群をもった赤ちゃんがこれらすべての障がいをもつとは限らず、これらの障がいのうちの一つか二つのみを持つ場合もあり、気づかれるまでに時間がかかることもあります。先天性風疹症候群がおこる可能性は、風疹にかかった妊娠時期により違いがあります。特に妊娠初めの12週までにその可能性が高いことが認められており、調査によって25−90%と幅があります。予防接種をうけることによって、成人女性なら妊娠中に風疹にかかることを予防し、または妊婦以外の方が妊婦などに風疹をうつすことを予防できます。(ただし妊娠中は風疹の予防接種をうけることはできません)
2005年度までは、「定期の予防接種」として生後12か月から90か月未満に1回風疹ワクチンが接種されていましたが、2006年度から麻疹とともに2回接種制度が導入され、1歳児(第1期)と小学校入学前1年間の幼児(第2期)に原則として、麻疹風疹混合(MR)ワクチンが接種されるようになりました。男性が予防接種をうけず自然感染したときには、妊娠中のお母さんなどに、大きくなってからであれば妊娠中の配偶者(妻)或いはパートナーなどに風疹をうつす可能性があります。そのため、1995年の制度改変では、接種対象者が生後12か月から90か月未満の年齢の男女小児および中学生男女になりました。
これに関連して、これまで風疹予防接種を受けたことがない成人男性も、なるべく早く予防接種をうけることをお勧めします。平成23年度の感染症流行予測調査によると、30代から50代前半の男性の5人に1人は風疹の免疫を持っていませんでした。20代の男性は10人に1人は風疹の免疫を持っていませんでした。先述の如く、大人が風疹にかかると、発熱や発疹の期間が子供に比べて長く、関節痛がひどいことがよくみられます。一週間以上仕事を休まなければならない場合もあります。また、脳炎、血小板減少性紫斑病、溶血性貧血などの軽視できない合併症をまれにおこすことがあります。 また、男性が風疹にかかると、妊娠中の女性が近くにいた場合、風疹をうつし、その赤ちゃんが先天性風疹症候群となって生まれる可能性があります。 自分と家族、そして周りの人々を風疹とその合併症から守り、生まれてくる赤ちゃんを先天性風疹症候群から守るためにも、これまで風疹の予防接種を受けたことがない場合は、成人男性でも可能な限り早く接種をうけられることをおすすめします。
【DPT-IPV4種混合ワクチン】
ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオの四種混合ワクチンです。従来の三種混合(DPT)に不活化ポリオ(IPV)をたしたものとなります。
ジフテリアは、現在発症はほとんど見られないまれな病気ですが、咽頭などに偽膜を形成して窒息死することもあります。その他の 症状は高熱、のどの痛み、犬吠様の咳、嘔吐などです。発病2〜3週間後に菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺をおこすこともあります。
百日咳は普通のかぜのような症状ではじまり、徐々に咳がひどくなり、犬吠様の咳となり、悪化すると顔をまっ赤にして連続性に咳込む程になります。咳のあと急に息を吸い込むので、小児では笛を吹くような音が出ることもあります。大人では典型的な症状が出にくく、診断が難しくなりがちです。乳幼児は咳で呼吸ができず、チアノーゼやけいれんをおこし、場合によっては窒息で死亡する例もあります。
破傷風菌はヒトからヒトへは感染せず、普段は土の中などに潜んでいて、傷口などからヒトの体内に侵入・感染します。菌の出す毒素のために、けいれんを起こしたり、死亡したりします。
ポリオは正しくは「急性灰白髄炎(poliomyelitis)」という病気です。ポリオの病原体はポリオウィルスです。ポリオウィルスは口からヒトの体内に入って感染しますが、ほとんどの場合は無症状か、あっても発熱・咽頭痛・嘔吐などのカゼ症状程度です。重大な麻痺につながる例は少なく、感染者の0.1〜2%程度に過ぎませんが、そうなった場合はまずい。ポリオウィルスがノドや小腸の粘膜で増殖後、血液を介して脊髄(や脳)に到達、そこの神経細胞に感染してこれを破壊してしまい、下肢を中心とした左右非対称性の弛緩性麻痺を起こします(要するに脚が動かなくなります)。基本的に治療法はなく、麻痺は生涯治りません。 患者のノドや便からは発症後しばらくポリオウィルスが出て来るので、これが周囲の人の感染源になり、流行を起こします。かつてポリオは世界注で流行し、多くの人を弛緩性麻痺にしてきました。 しかし1960年前後に相次いで登場したポリオワクチンにより、多くの国で流行は抑制され、2012年現在、あと一息でポリオウィルス撲滅という所まで来ています。
【破傷風ワクチン】
破傷風ワクチンは10年前後で効果が薄れてしまいます。20〜40歳台で、子供のころにDPTワクチン(3種混合)のワクチンを接種したことがある方は1回の接種で問題ありません。 破傷風やDPTワクチン接種の既往がない方や、50歳以上の方は、3回接種が必要です。2回目の接種は初回から4〜8週あけて行います。 3回目は初回接種から6〜18ヶ月の間に接種を行います。
【狂犬病ワクチン】
哺乳動物の捕獲や研究に従事する方や、動物と直接接触する機会が多くなる長期の海外旅行予定の方、都市部から遠く離れ、現地にて緊急対応ができない地方部に滞在する方におすすめします。感染した哺乳動物の唾液や分泌物の中に狂犬病ウイルスは存在し、唾液のついた爪で引っ掻かれても感染の危険があります。狂犬病を発症すると現在の医学では治療法がなく、ほぼ100%が死亡する怖い病気です。万が一、感染した動物に咬まれてしまった場合ですが、事前に予防接種を受けていた方の場合、追加接種(2回:0、3日)が必要です。すでに接種を受けていても追加接種が必要で、追加接種は、出来るだけ早期に受けることが必要です。病院でワクチンを受けた日を0日とし、3日後に2回目を受けます。事前に予防接種を受けていない方の場合、傷の程度によっては、狂犬病に対する血清(γ?グロブリン)の局所注射とワクチンを5回接種(0、3、7、14、28日)を行います。
【ロタウイルスワクチン】
・ロタテック 3回経口接種
・ロタリックス 2回経口接種
ロタウイルスによるウイルス性胃腸炎を予防するための経口ワクチンです。お子様のウイルス性胃腸炎の原因のうちで、一番重症になりやすいのがロタウイルスです。約2日の潜伏期を経て、主に乳幼児に4〜5日続く強い嘔吐・下痢症状をもたらします。「下痢便の色が白くなる」事がよく知られていますが、その他、発熱も30?50%と高頻度でみられます。激しい下痢症状のため脱水にもなりやすく、まれですが繰り返すけいれんや脳炎など重篤な合併症も引き起こすことがあります。根本的な治療法がないため、ワクチンによる予防が大切です。現在、世界120ヶ国以上でロタウィルスワクチンが導入されており、あるデータによると、ロタウィルスワクチンにより、ロタウィルス胃腸炎総数を約70%減らし、重症例を約90%減らし、入院を約95%減らすといわれています。
「ロタリックス」は最も頻度の高いロタウィルスであるG1P[8]型にのみ対応した1価ワクチンですが、交叉免疫性が強く、他型に対しても免役を作ります。具体的にはG2P[4],G3P[8] G4P[8],G9P[8]型にも効きます。つまり多価ワクチンと同等の効果があるわといえます。一方、「ロタテック」は、G1,G2,G3,G4,P[4]の5つの成分を含んでいて(「5価ワクチン」)、頻度的に上位4種であるG1P[8],
G2P[4], G3P[8], G4P[8]の全てを抑えます。選択に迷うところと思われますが、二者の効果の違いは大きくはないといってさしつかえありません。ロタリックス” の場合、2回接種となります。ただしその接種時期には制限があります。1回目は生後6週以降、20週までに2回目は生後10週以降、24週までに、となります。 「ロタテック」 の場合は、3回接種となります。ただしこれも接種時期に制限があり、1回目は生後6週以降、24週までに2回目は生後10週以降、28週までに3回目は生後14週以降、32週までに、となります。生ワクチンのため、4週間以上間隔をあけなければなりません。
0歳児は他にも接種が必要なワクチンが多数ありますので、Hibや小児用肺炎球菌ワクチンと同時接種するのがおすすめです。具体的には1回目は2ヶ月齢に、Hibや小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチンと一緒に。2回目は3ヶ月齢に、Hibや小児用肺炎球菌ワクチン・DPT・B型肝炎ワクチンと一緒に。3回目(ロタテック)は4ヶ月齢に、2回目と同様にが良いでしょう。ロタリックスは腸重積症の既往のあるお子様や、腸重積症を起こしやすい腸の病気をお持ちのお子様はお受けになることができませんのでご注意ください。
看護、医療実習前あるいは海外留学前に抗体価を測定する必要のある方、測定の上で予防接種が必要な方もお気軽にお問合せください。
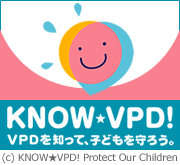
任意接種ワクチン価格表
抗体価測定価格表
![]() MIRAI MEDICAL CLINIC
MIRAI MEDICAL CLINIC
MIRAI MEDICAL CLINIC MYOGADANIみらいメディカルクリニック茗荷谷
みらいメディカルクリニック茗荷谷
〒112-0012
東京都文京区大塚1-4-15 アトラスタワー茗荷谷 202
TEL 03-3943-0123
FAX 03-3945-9123